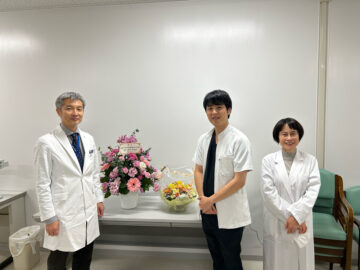長崎大学病院 乳腺センター/病理診断科・病理部
センター長/教授 山口 倫
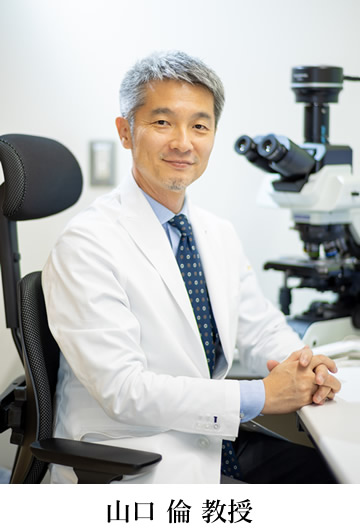
センター内で、乳腺疾患の病理を担当する山口倫(やまぐち りん)と申します。乳腺センターのセンター長を拝命し、病理診断科・病理部と兼務させていただいております。センター長として大学内各部門と連携を深めるとともに、県内の医療機関と協力し、大学病院内及び県内で乳腺診療が円滑かつ効果的に行えるよう支援して参ります。また、乳腺疾患における精度の高い病理診断を、一例、一例丁寧に行うとともに病理学に関連する研究および教育の推進にも尽力していく所存です。
私は、医師として外科からキャリアをスタートし、その中で病理の重要性を痛感し、大学院で病理の道に進みました。肝臓病理の研究を経て、現在乳癌を専門分野として取り組んでおります。現在は、日本乳癌学会の理事、日本臨床細胞学会の常務理事を務めています。また世界との交流の中で、WHO分類第5版、第6版の策定にも携わり、乳癌取扱い規約の委員長も務めています。
私が診断において大切にしている言葉があります。それは、乳腺病理の大家である故坂元吾偉先生からいただいた次の教えです。
「病理診断は一例一例が真剣勝負であり、その真剣勝負にすべて勝たねばならない。」
この言葉を常に胸に刻み、診断の先に待つ患者さんのために、一例一例を全力を尽くして向き合って参ります。そして、長崎大学の伝統に恥じぬよう、微力ながら粉骨砕身して職務に取り組む所存です。
病理とは?
「病理」と聞いても、馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。基礎研究のみをイメージされることもあるでしょう。しかし、病理には大きく分けて人体病理学 (病気に関わる解剖、病理診断) と実験病理学 (患者さんから得られる検体を用いた研究) があり、病理医とはこれらの業務を担う医師のことを指します。
病理診断科・病理部は診断に特化した臨床系の一部門であり、その主な仕事は病理診断です。病理診断とは、例えば、胃の内視鏡検査で良悪性の鑑別が必要な陥凹性病変やポリープが見つかった場合、その組織の一部を採取し、顕微鏡で(最近ではホールスライドイメージングで)良性あるいは悪性を判断し、その結果を臨床医に報告することです。病理医は、医療の中で裁判における裁判官に例えられるような役割を担っています。すなわち、患者さんの診断医おいて「最終診断」を下す責任を負い、その診断が患者さんの治療方針に直結する重要な役割を果たしています。病理診断は、医療の中核を支える仕事です。
乳腺病理は、多臓器に比べて多彩な形態を示すため、専門病理医であっても診断が難しい分野とされています。これまでの経験を活かし、当センターでは精度の高い診断を提供することを目指して参ります。
学生の皆さん、研修医や病理に興味のある先生方へのメッセージ
長崎大学病院 乳腺センター/病理診断科・病理部で一緒に仕事してみませんか?
私は、2023年4月より長崎大学病院 病理診断科・病理部教授を拝命し、2024年9月からは乳腺センター長も兼務しています。
病理医の仕事は、患者さんの治療方針を左右する「最終診断」を下す、責任重大でありながらやりがいのある職種です。また、患者さんの検体を直接預かる立場でもあり、承諾を得てその検体をもとに研究を進めることも可能です。
乳腺に興味のある方へ
乳腺病理に興味をお持ちの先生方、ぜひ一緒に研究と診断に取り組んでいきましょう。私は、2006年に癌研有明病院で坂元吾偉先生、秋山太先生から乳腺病理を学びました。現在は、日本乳癌学会の理事、日本臨床細胞学会の常務理事を務めています。また世界との交流の中で、WHO分類第5版、第6版の策定にも携わり、乳癌取扱い規約の委員長も務めています。これまで国内外で学んだ知識や経験を次世代に伝え、私の後継者を育てたいと考えています。
病理の魅力
病理は自分の時間を大切にできる科でもあります。育児などを考える女性医師や、自分のペースで働きたい方には特に向いています。また、患者さんと直接的なコミュニケーションが苦手な方でも顕微鏡に向き合いながら黙々と仕事を進めることが可能です。また、特に内科系、外科系の先生方は、自分たちが採取した検体がどのようにミクロの世界で見えるのか、日常の臨床業務から一旦離れ、一時的に病理の世界で過ごし、診断や研究を行うことも、有意義な時間となるでしょう。
キャリアの可能性
病理医としての道は、これまでの経験によって異なりますが、数年の経験後に専門医試験を受けることが一般的です。
収入面についても、大学の給与に加え、診断業務や解剖出張で得られる収入があります。専門医資格を取得すればさらに幅広い選択肢が広がり、病理医は日本で深刻に不足しているため、需要が非常に高い職種です。将来的に開業の道も選べます。また、AIの発展が進んでも、最終的な確認や検証は病理医にしかできません。専門家としての需要は今後も続くと考えています。
どんな些細なことでも結構です。ご興味があればせひご相談ください。一緒に未来の医療を支える道を模索していきましょう!
1204書籍紹介